

![]()
�@�k���N�́A�����R���͒P��R�̐�����鍑�ƂŁA�ʓr�̗��R���Q�d���◤�R�i�ߊ����͒n��R�i�ߊ��̂悤�ȐE�ӂ͂Ȃ��B�����R�̐��ł͂��邪�A���̂ŌR��iService�j��\������Ƃ��ɂ́A�u�l���R���R�v�Ƃ����\�����g�p����悤�ł���B�啔���̑�3���E���Ƃ������ł���悤�ɁA�n��R���S�̐�͂ɂ�����
��߂��d�����|�I�ŁA�l���R�n��R�́A�l���R���̂��̂��ƌ�����B
�@�l���R�n��R������ōŏ㋉�Ɉʒu���鑶�݂͌R�c�ł���B50�`70�N�܂ŏW�c�R�Ƃ����Ґ������݂������A���̏�ݕҐ����ł́A�R�c���ŏ㋉����ł���B�������A�펞�ɂ́A�R�c���㋉�̏W�c�R�A�O���R���͑O���i�ߕ����ݒu�����\���͈ˑR�c���Ă���B
�@�k���N�̌R�c�́A20�ō\������Ă���B�R�c�̓���́A�O���n�ѐ��K�R�c4�A����n�搳�K�R�c8�A��ԌR�c1�A�@�B���R�c4�A�C���R�c2�A���h�i1���ł���B
�@�R�c�̉��̒���Ƃ��ẮA��������t�c/���c��33�i���̓��t�c����26�j�A�����t�c��37�A�@�B�������t�c/���c��25�i�啔�����c�̐����ł���B�j�A��Ԏt�c/���c��15�i�啔�����c�̐����ł���B�j�ł���B
1)�R�c�̔z�u�����i���_���o�ߒ��́A�R�c�z�u�����Q�Ɓj
☞�M�҂́A��N�܂Ŏ��]���i���]�㗬�j��10�R�c�A���]���i�����]�㗬�j��11�R�c�����Ԃ��Ă�����̂Ɛ��肵���B�������A�\�E���V��1996�N12��10���t������A�E�k�҂ł���k���N�Љ���S���������z����
��J�œ����]��n��Ƃ��A�����x����S�����镔����10�R�c�������ƌ�������Ƃ���A���]���i���]�㗬�j��11�R�c�A���]���i�����]�㗬�j��10�R�c�����Ԃ��Ă�����̂Ɣ��f���C�������B
☞�V����2000�N10�����Ɍf�ڂ��ꂽ���`�����t���L�҂́u�n������DMZ�A�l���R��N���[�g�ƂȂ�̂��H�v�Ƃ�����ڂ̋L��������A2000�N���ɖk���N�̍őO���R�c2���ʒu��
����ւ����Ƃ����B�Ċؗ��҂́A�l�H�q���ł����ߑ��ł����A�@�I���@�i�H����A���͎ғ��j�ł����m�����Ƃ����B���`�����t���i���T�ԓ����L�ҁj�̏ꍇ�A�ߋ���������A�����W���[�i���ݐE���ォ��͂̕��Ă݂�A�����ɕ��L���\�[�X�Ԃ������Ă���l���ƍl������B�]���āA�k���N�R�c�̈ʒu���ύX���ꂽ�Ƃ����ނ̕��́A�M����������悤�ł���B�ǂ̌R�c���ʒu��ύX�����̂��́A�܂����J����ĂȂ������B
☞��������2000�N12�����́A�u�Ő��s425�@�B���R�c�������A�Ȃ��ADMZ�t�ߎc���v�Ƃ����L���ɂ����āA���k��B�Ɏi�ߕ���u���Ă���425�R�c��2000�N�ċG�P���̂��߁A�]����
�����тɑO�i�z�u���ꂽ��A�P�����I��������ɂ����A���Ă��Ȃ��ƕ����B���̋L�����V����2000�N10�����̖k���N�O���R�c�ʒu�ύX�Ɗ֘A�������̂��A�����Ȃ���A�ʓr�̓��e�Ȃ̂��́A���J���ꂽ��������͊m�F�ł��Ă��Ȃ��B���������ɕ��ꂽ���̂�����A�֘A������悤�����A�@�B���R�c�̈ړ����Ƃ���A�l�H�q���ŕߑ��ł��Ȃ��Ȃ����Ƃ���A�ʓr�̎����ƍl������B�L�����쐬���ꂽ2000�N11������ɖk���N�̑�425�@�B���R�c�́A�����k��
��B�ł͂Ȃ��A�]��������ߗׂɑO�i�z�u����Ă���A���������Ԓn�ւ̕��A���m�F����Ă��Ȃ��B
☞2000�N12���Ɍ��J���ꂽ2000�N�ő�ؖ������h�����ɂ́A�ʂɈقȂ���ُ��Ȃ��A1999�N�ō��h�����Ƃقړ���Ȑ��������Ă���B
���n�}�́A�嗪�I�Ȓ��Ԉʒu��\���������̂ŁA���m�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B

| �R�c���� | �i�ߕ����ݒn | �NJ���� | ���l |
| 1�R�c | �]�����̗z�S | �x������� | �O���n�ѐ��K�R�c�A���N�푈�Q�� |
| 2�R�c | ���C�k�����R�S | �x��������� | �O���n�ѐ��K�R�c�A���N�푈�Q�� |
| 3�R�c | ��Y�����s�]����� | �����쓹 | ��r�I�������ꂽ������K�R�c�A���N�푈�Q�� |
| 4�R�c | ���C�쓹�C�B�s | �x������� | ���O���n�ѐ��K�R�c�A���N�푈�Q�� |
| 5�R�c | �]�����ɐ�S | �x������� | �O���n�ѐ��K�R�c�A���N�푈�Q�� |
| 6�R�c�H | ���Ò����s | �����k�� | 95�N�ɔ��v�����������A��́H�A���N�푈�Q�� |
| 7�R�c | �����쓹�����s�H | �����쓹 | ������K�R�c�A���N�푈�Q�� |
| 8�R�c | �����k����B�s�H | �����k�� | ������K�R�c�A�ʖ��H�ꋳ�����A���N�푈�Q�� |
| 9�R�c�H | ���R�����ÁH | �]�������k | 90�N��ȍ~�m�F�A�ŋߒ��Ԓn�ړ� |
| 10�R�c | ���]���]�E�s | ���]�� | 90�N��ȍ~�n�݁A�����Ď��C�� |
| 11�R�c | ���]���b�R�s | ���]�� | 90�N��ȍ~�n�݁A�����Ď��C�� |
| 12�R�c | ���C�k���H | ���C������H | 90�N��ȍ~�n�� |
| �H�R�c | �]�����H | �]�����H | 90�N�㒆�t�ȍ~�V���Ɋm�F |
| 108�@�B���R�c | �ܘV�H | �| | ���������3����T���Ώ㗤���y�ї\�� |
| 425�@�B���R�c | �����k����B | �| | ���h��y�ёΏ㗤���y�ї\�� |
| 806�@�B���R�c | �]�������� | �| | ���������2��� |
| 815�@�B���R�c | ���C�k�������S | �| | ���������2����A���͂Ȋj�S�R�c |
| 820��ԌR�c | ���C�k�������@�s�R�u���� | �| | ���������2����A���͂Ȋj�S�R�c |
| 620�C���R�c | ���C�k���V�k�S | �| | ��������Η͎x���y�ї\�� |
| �]���C���R�c | ������ʎs�]���S | �| | ��������Η͎x���y�ї\�� |
| ���h�i | ������ʎs | �����~ | ���͂Ȑ��K�R���� |
�@�O���n�ѐ��K�R�c
|
1�R�c�i�]�����̗z�S�j�F�R�c���S�ݑP���� | |
|
2�R�c�i���C�k�����R�S�j�F�R�c�����i�A�叫�i97�N2���叫�ɏ��i�j | |
|
4�R�c�i���C�쓹�C�B�s�j�F�R�c���鑊���叫�i97�N2���叫�ɏ��i�j | |
|
5�R�c�i�]�����ɐ�S�j�F�R�c�������M�叫�H�i97�N2���叫�ɏ��i�j |



 �i�ʐ^������S�ݑP�A�����M�A���i�A�A�鑊���j
�i�ʐ^������S�ݑP�A�����M�A���i�A�A�鑊���j
�@�k���N�ł́A�x����t�ߒn���O���n�тƂ����B�����A�O���n�тƂ́A�؍��̗p��őO���n��Ǝ����Ӗ��ł���B�O���n�ьR�c4�́A�@�b/�@�B���R�c�����O������ʓI�Ȑ��K�R�c���ł͍ŋ��ƌ�����B�����Ő��K�R�c�Ƃ����p��́u���K�v�́A�@�b�y�ы@�B���R�c�ł͂Ȃ��ʏ�̌R�c�iConventional Corps�j�Ƃ����Ӗ��ł���B
�@1�A2�R�c�̏ꍇ�A���N�푈�J�n�������瑶�݂��Ă��������ŁA4�A5�R�c�����N�푈���ɑn�݂��ꂽ�`����L���鐸�s�����ł���B���ɁA1�R�c��2�R�c�́A���̌R�c���i�������A�L���̍ۂɑO���R�Ɋi�グ�����\��������Ɛ��肷����{�����i�R�������j������B�O���R�Ɋi�グ�����ꍇ�A1�R�c���������O���i�ߊ��A2�R�c������������i�ߊ���S��������̂Ɨ\�z���Ă���B
�@�R�c�ʂ̓��������Ă݂�A1�R�c�́A�z�u���ꂽ�n��̒n���I�ȓ�����A�@�b�|�@����͂������k���Ґ�����Ă�����̂��Ɛ���ł���B��2�R�c�Ƒ�5�R�c�́A�e�X汶�R�����ƓS�������̏o�������������Ă���R�c�ł��邱�Ƃ���A���̐�͂�����Ȃ��̂Ɨe�Ղ��������邱�Ƃ��ł���B
�@4�R�c�̏ꍇ�A�O���n�ьR�c�����ADMZ�ڊNJ����镔���ł͂Ȃ��B���̂��߁A4�R�c�̏ꍇ�A���̑O���R�c�ƈقȂ���������݂���B������ƁA�t�c�y����������ݒu���ꂽ�����A4�R�c�����t�c�́A���̌R�c���
�͂邩�ɒx��Čy����������ݒu���ꂽ�B���̂悤�Ȃ��Ƃ���A4�R�c�����̑O���R�c���D�揇�ʂ���ɗ��2�����R�c�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B4�R�c�́A�U���������ȏꍇ�A2�R�c�Ɍ㑱����\�E���U���̎�͕����̒���1�ƂȂ蓾�邽�߂ł���B�A���ҋy�ђE�k�ҒB�̊e��،������Ă݂�A4�R�c�́A�؍��C���ɂ�鉩�C���C�ݒn��ւ̏㗤���ɔ�����C�����L���Ă���Ƃ����B���ɍŋ߁A��12�R�c�̑n�݂ɂ��4�R�c�̕��S�������y������A�L���̍ہA�U�����ɑ�4�R�c��
���������ʊ��ɓ����ł���������������ꂽ�B
�@1999�N7��18���A�A���ʐM�́A�u��ǁv�̔��������p���āA1998�N���A�k���N�́A1�R�c��4�R�c��170mm�����C��240mm���P�b�g�C�e�X40�]���V���ɔz�u�����ƕ����B�e40�]��A�v80�]��ł��邱�Ƃ���A�T��1�C�����c�ɊY�������͂��lj��Ŕz�u���ꂽ�v�Z�ł���B
�@2�R�c������v�A���҂́A1989�N9���ɋA������2�R�c9�t�c�������i���W�������т�����B
�A�����n�搳�K�R�c
|
3�R�c�i����j�F�R�c�������Z�叫 | |
|
7�R�c�i����j�F�R�c���H | |
|
�H�R�c�i�]���j�F�R�c���H | |
|
12�R�c�i���C�j�F�R�c���鏟�j�㏫ |

 �@90�N��ȍ~�A�����n���2�R�c�i�H�R�c�A12�R�c�j���n�݂���A�h��c�[�������������ꂽ
�悤�ł���i�ʐ^�́A�����Z�A�鏟�j�j�B
�@90�N��ȍ~�A�����n���2�R�c�i�H�R�c�A12�R�c�j���n�݂���A�h��c�[�������������ꂽ
�悤�ł���i�ʐ^�́A�����Z�A�鏟�j�j�B
�@�����n��R�c���A3�A7�R�c�́A�S�Ē��N�푈���ɑn�݂��ꂽ�`�����镔���ł���B
�@����3�R�c�́A��s���ɋߐڂ����R�c�ŁA��d�������Ȃ����̂Ɛ��肳���B3�R�c�̏ꍇ�A�O���n�ьR�c���x�̐�͔͂����Ă��Ȃ����A���̌���R�c�̂悤�Ȏ�̌R�c�ł͂Ȃ������悤�ł���B�ߋ��A�ꕔ���{�����ɂ����āA3�R�c���@�B���R�c�ɕ��ނ����̂��A�S�������̂Ȃ�
���̂ł͂Ȃ��B�����A�ŋ߂ɒ����y�ь���n��ɐ��̌R�c���lj��őn�݂���A��Ƃ��Ėh�q�̂��߂̕ʓr�̐��K�R�c�ł��镽�h�i�����n�݂��ꂽ�ŁA3�R�c�̐�͂������㉻�����\��������B�E�k�қ�
�`���t�@���㍲�̏،��ɂ��A�k���N�ɂ����Ċe���i�ߕ���PC�ʐM�Ԃ�ݒu�����Ƃ��A�ŏ���
�t�͎��Ƃ����{�����R�c��3�R�c�������ƌ��A�����ł�PC�ʐM�Ԃ��ǂ��\�z����Ă���Ƃ����i�A���ʐM99�N5��14���t�j�B
�@7�R�c���T��51�N�O�����ɓ��C���R��т�UN�R�̏㗤���ɑΉ�����ړI�őn�݂��ꂽ�����ŁA53�N���ɂ́A��������Ŏ���o�����L���Ă������K�R�c�������B�������A�����_�ł́A���Ԉʒu��A��͔z�����ʂ�������������̂ł��邱�Ƃ�e�Ղ����肷�邱�Ƃ��ł���B
�@98�`99�N�ō��h��������Ɍ���A����ƌ��R�����Ԓ����n��ɍ��܂Ő��̂��m�F����Ă��Ȃ�1�R�c�����݂��Ă���悤�ł���B�ߋ��A���̒n��ɒ��Ԃ��Ă���9�R�c�́A��6�R�c�NJ��n��ł�������k���n��Ɉړ��������̂Ɛ��肳��A����ɒP�̃i���o�[���ڂ̌R�c���n�݂��ꂽ�悤�ł���i���́A�����炩�ł͂Ȃ��B�j�B
�@��12�R�c�́A90�N�㒆�t���n�݂��ꂽ�R�c�ŁA���C������n��ɒ��Ԃ��Ă���B��12�R�c�́A�L���̍ہA�O���n�ьR�c�̓�N��A��2�R�c���4�R�c�NJ��n����x������C����
�тт��悤�ł���B���̊O�ɁA�L���̍ہA�O���R�c���x������C����S�����邱�Ƃ����邾�낤�B
�B����n�搳�K�R�c
|
8�R�c�i���k�j�F�R�c�����e�Y�㏫�H�i�O8�R�c�������M�́A97�N�㔼�����A5�R�c���ɕ�E�ύX�H�j | |
|
9�R�c�i�����j�F�R�c���H | |
|
10�R�c�i���]�j�F�R�c���C�z�j�㏫ | |
|
11�R�c�i���]�j�F�R�c���H |
 �@����n��ɂ́A�������ԁA6�R�c��8�R�c�̂ݒ��Ԃ��Ă������A90�N��ȍ~�A2�R�c���V���ɑn�݂��ꂽ�i�ʐ^�́A
�C�z�j�j�B
�@����n��ɂ́A�������ԁA6�R�c��8�R�c�̂ݒ��Ԃ��Ă������A90�N��ȍ~�A2�R�c���V���ɑn�݂��ꂽ�i�ʐ^�́A
�C�z�j�j�B
�@8�R�c�̏ꍇ�A�ߋ�70�N��ɂ́A�ʖ��H�ꋳ�����ƌĂ��ʁA�����t�c���W���I�ɕۗL�������͂Ȑ헪�\�������������B���̒n��ɌR���H�ꂪ�������߁A
�R���H��ɋΖ�����Ⴂ�\����J���҂��R�c�\����͂ɋz���ł������߂ł���B�������A�ŋ߁A���̒n��ɑ�10�R�c�i��11�R�c�H�j���lj��őn�݂��ꂽ���߁A8�R�c�̐�͂��������U�����\��������B����8�R�c�i�y���������w���ǂ̑O�g�j��8�R�c�̒��Ԉʒu�����Ă���A�����������o����ꍇ�����邪�A�S���قȂ镔��
�Ȃ̂Ō���Ȃ��悤�B�ꕔ�}�X�R�~�́A99�N��O�サ�āA8�R�c���V���ɑn�݂���A�U�����̂��u593��A�������v�A�i�ߕ����ݒn�́A�����k�����B�S�A�i�ߊ��́A���e�Y�㏫���ƕ������Ƃ�����i�؍�����99�N10��17���t�j8�R�c���V���ɑn�݂��ꂽ
���̂��Ƃ�����e�͌��ƍl�����邪�A���̓��e�͍�����������e�ƍl������B�M�҂̍l���ł́A���炭90�N�x���t�A��11�R�c�n�݂ɂ��8�R�c�̊NJ���悪�k������A8�R�c�i�ߕ����ړ]�����̂��u�n�݁v�Ƃ��ĕ����̂ł͂Ȃ��̂��ƍl������B
�@8�R�c�܂ł́A����70�N��̎����Ŋm�F����邪�A9�R�c�y�т���ȍ~�n�݂��ꂽ�R�c�́A�؍��������ł́A90�N��ȍ~���瑶�݂��m�F����Ă���B�k���N�ɂ����ĐV����������n�݂�����A�؍�����������m�F����܂Ŏ��ԓI�i�������݂��邱�Ƃ���A9�R�c�̑n�݂́A�������1980�N��܂ők�����̂Ɛ��肳���B���E�l�����͕��������ł���C�t���㏫�̌o���ɑ��鍑���}�X�R�~�̂���ɂ��A��9�R�c��1980�N���߂đn�݂��ꂽ�Ƃ��A����R�c�����C�t���������Ƃ����i��������1999�N9��10���t�j�������m�Ȃ��̂Ƃ���A9�R�c�̑n�ݎ��_�́A1980�N�ƂȂ�B
�@9�R�c�̏ꍇ�A�ߋ��A�]�����ɒ��Ԃ������A���݁A�����Ɉړ������悤�ł���B98�`99�N���h�����ɂ��A6�R�c����̂��ꂽ�v�Z�����A���炭�A�u6�R�c�N�[�f�^�[���v�Ɗ֘A�����[�u�ł���悤�ł���B�ߋ��A6�R�c�������k���ɒ��Ԃ���Ƃ��A�R�c�i�ߕ��́A���Îs�Ɉʒu�����B�M�҂́A6�R�c���N�[�f�^�[�Ɗ֘A���ĉ�̂���A�����9�R�c����6�R�c���Ԓn��ł�������k���Ɉړ��������̂Ɛ��肵�Ă���B
�@���O�ʐM�ɕ��ꂽ�Ƃ���ɂ��A10�R�c��11�R�c�̏ꍇ�A�E�k�ҊĎ��̂��߂̍����x���ړI��95�N�����n�݂��s��ꂽ�������Ƃ����B���m�ȑn�ݖړI�͕�����Ȃ����A�Ƃ������A���̒n��̌R�c�n�݂́A�����I�Ȑ�͑����Ƃ������͎w���̌n�����Ƃ��������ŗ������ׂ����낤�B
�C�@�b/�@�B��/�C���R�c
|
108�@�B���R�c�i�]���H����H�ܘV�j�F�R�c���������叫 | |
|
425�@�B���R�c�i���k��B�j�F�R�c���H | |
|
806�@�B���R�c�i�]��������j�F�R�c���H | |
|
815�@�B���R�c�i���C�k�������S�������j�F�R�c���H | |
|
820��ԌR�c�i���C���R�u�����j�F�R�c���H | |
|
620�C���R�c�i���C�k���V�k�S�H�j�F�R�c���A�_�Ϗ㏫ | |
|
�]���C���R�c�i������ʎs�]���S�H�j�F�R�c���H |

 �@�����́A�啔��80�N��ȍ~�n�݂��ꂽ�V�ҕ����ŁA���̓�815�@�B���R�c��820��ԌR�c����͂��ł����������ƒm���Ă���B108�@�B���R�c�A806�@�B���R�c�̏ꍇ�A�ߋ��A9�A10�@�B���R�c�Ɛ��肳��Ă��������Ɠ���̂ł���i�ʐ^�́A������������A�A�_�ρj�B
�@�����́A�啔��80�N��ȍ~�n�݂��ꂽ�V�ҕ����ŁA���̓�815�@�B���R�c��820��ԌR�c����͂��ł����������ƒm���Ă���B108�@�B���R�c�A806�@�B���R�c�̏ꍇ�A�ߋ��A9�A10�@�B���R�c�Ɛ��肳��Ă��������Ɠ���̂ł���i�ʐ^�́A������������A�A�_�ρj�B
�@425�@�B���R�c�́A���h��T���Ώ㗤�h��̖�����S������R�c�ƌ����A�헪�\���̖��������s�ł���悤�ł���B1999�N9���A����h�ύ���č��֘A�ɂ��A�k���N425�@�B���R�c����362�@�����c�A417�@�����c�A815�C�����c�ꉺ���������99�N4�����畔���ʒu��ύX�������Ƃ�����Ƃ����i��ؖ����V��99�N9��29���t�j�B2000�N
�āA425�@�B���R�c�́A�P���̂��߁A�]��������t�߂ɑO�i�z�u���ꂽ���A�P�����I������2000�N11�����݂܂ł��A�����k����B�ɕ��A���Ă��Ȃ��B���̎����������������2000�N12�����́A425�R�c����3�����̕��͂�200�]��̐�Ԃ�ۗL���Ă���Ɛ��������B
�@108�@�B���R�c���A�Ώ㗤�h��̖����Ƌ��ɓ����n���3������A�헪�\���̖����𐋍s�ł�����̂ł���B108�A425�@�B���R�c�̂悤�Ȍ���n��@�B���R�c�́A���̋@�B���R�c����̂Ɛ��肳���B
�@�k���N�@�B��/��ԌR�c�̏ꍇ�A3���̒P�̃i���o�[�������Ă��邪�A���ꂪ���ۂ̒P�̃i���o�[�Ȃ̂��A�����Ȃ���A820�P�����̂悤�ȋU�����̂ɉ߂��Ȃ����̂Ȃ̂����炩�łȂ��i���O�ʐM���������Ă݂�A�U�����̂����m��Ȃ��Ƃ����j���A���X��
�Y�킹�Ă���B�j�B
2)�R�c�̕Ґ�
�@���K�R�c �| �ύt�̎�ꂽ��͍\���������Ă��邪�A���q��͂����͕s��
 �@�����̐}�\�́A�C���^�[�l�b�g�Ɍ��J����A�����ł��b��ƂȂ��Ă����ĊC�������ǎ����ɏo�Ă������̂ł���B
�@�����̐}�\�́A�C���^�[�l�b�g�Ɍ��J����A�����ł��b��ƂȂ��Ă����ĊC�������ǎ����ɏo�Ă������̂ł���B
�@���̐}�\�ɂ��A���K�R�c�̎��͂́A�����t�c5�A��ԗ��c1�ō\������Ă���B
�@�k���N�̐��K�R�c���v12�ł��邱�Ƃ���A�ŏ���60�����t�c�����݂��Ă����A���̕Ґ�����[�����邱�Ƃ��ł���B
�@���h����99�N�łɂ��A�k���N�����t�c/���c�̑����́A33�ɉ߂��Ȃ��BMB 98�`99�N�łɂ��A�k���N�����t�c�̐�����26�ŁA�Ɨ��������c��3�ł���B
�@���ǁA5�t�c�Ƃ����Ґ�����[�����邽�߂ɂ́A�����t�c�i�\���t�c�j�܂Ŋ܂߂�O�Ȃ��B���h����99�N�łɂ��A�k���N�����t�c�̑�����37�ŁAMB�ɂ��Ζk���N�̗\�������t�c��26�A�\���������c��18�ł���B
�@���ǁA�O���n��4���K�R�c�i1�A2�A4�A5�R�c�j��5�t�c���S�Č����t�c�����ō\������Ă���A������K�R�c�́A����1�̌�������t�c��ۗL����̂�����Ƃ����Ӗ��ł���B3�R�c��12�R�c�̂悤�Ȓ����n�搳�K�R�c��
������Ȃ����A8�A9�A10�A11�R�c�̂悤�Ȍ���n�搳�K�R�c�́A�����t�c�����ŕҐ�����Ă���\��������B
�@�R�c�����͂Ƃ��ẮA�_�����c1�A�y�������c1�A��@���1���Ґ�����Ă���B�k�،���������78�N�ɔ��s�����u�k�،R���_�v�ɂ́A�R�c���������Ƃ��āu�C����@���v���Ґ�����Ă���Əo�Ă��邪�A���̐}�\��ɂ́A�u�C����@���v���o�Ă��Ȃ��B����ɁA70�N��̎����ɂ͊m�F����Ă��Ȃ������u�d�q�����v���V���ɕҐ����ꂽ���̂ƌ�����B
�@�R�c�C����͂Ƃ��ẮA2���c���o�Ă��邪�A1���c�͎����C���A1���c�͑��A�����P�b�g�i�k���N���̕��˖C���c�j�Əo�Ă���B����́A70�N��̎����Ɠ���̂��̂ł���B�����A70�N��̎����ɏo�Ă���160mm�����C�A���͌������A�S�ʓI�ȖC���Η͋����ɂ��A�R�c�����̔����C�A���͉�̂��ꂽ�悤�ł���B
�@�ΐ�ԃ��P�b�g������R�c�����ŕҐ����ꂽ���Ƃ��A70�N��ƕω����Ȃ��B���̑��H���A���A�h��C�A���A�ʐM����A���w����A�㖱�����́A��{�I��70�N��ƍ��ق��Ȃ��B
�@�k���N�̐��K�R�c�́A�S�ʓI�Ɍ���ƁA�ύt�̎�ꂽ��͍\���������Ă��邪�A���R�q���͂������s�����Ă���悤�ł���B���̐}�\�̕Ґ���́A�O���n�тɒ��Ԃ������K�R�c�ɂ����Y�����A�����n��y�ь���n�搳�K�R�c�̏ꍇ�A���̐}�\��̕Ґ����͐�͂�
���Ȃ����Ă�����̂Ɛ��肳���B
�A�@�B���R�c �| �ޗႪ�Ȃ��Ɠ��ȕҐ��A�R�c�S�̐�ԕۗL���ʂ�155��H
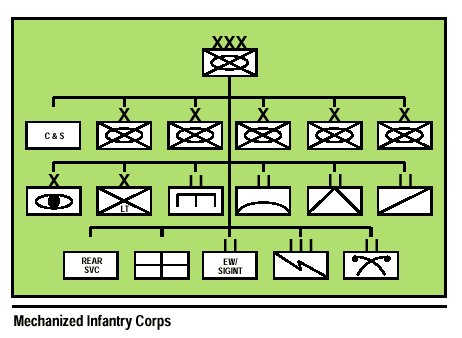 �@�k���N�̋@�B���R�c�́A�@�B���������c5���厲�ɕҐ�����Ă���B���̎����ʂ�Ƃ���A�R�c�����̐�ԗ��c�����͑��݂��Ȃ��B
�@�k���N�̋@�B���R�c�́A�@�B���������c5���厲�ɕҐ�����Ă���B���̎����ʂ�Ƃ���A�R�c�����̐�ԗ��c�����͑��݂��Ȃ��B
�@�k���N�@�B���������c�ɂ́A����1�̐�ԑ���i31��ۗL�j�̂ݕҐ�����Ă��邱�Ƃ���A�P���v�Z�ł́A�@�B���R�c�S�̂̐�ԕۗL���ʂ́A155��ɉ߂��Ȃ��B����́A�@�B���R�c�̐�ԕۗL����
�Ƃ��ẮA�����s�����������Ƃ����������������Ƃ��ł��Ȃ��B155��Ȃ�A������A�@�B���t�c���̐�͂ɉ߂��Ȃ����߂ł���B
�@�k���N�Ȃ�̌y�ʉ����ꂽ�Ґ����Ɨ������邱�Ƃ��ł��邪�A���K�R�c�̐�ԕۗL���ʂƔ�r���Ă݂�A�K�����������ł͂Ȃ����Ƃ�������B�ĊC�������ǂ̎����ʂ�Ƃ���A���K�R�c�ɂ́A�R�c�����Ő�ԗ��c1���Ґ�����Ă���A�����t�c�ɂ���ԑ��1�����Ґ�����Ă���B��ԗ��c�ꉺ�ɂ́A��ԑ��4�����Ґ�����Ă���A�����t�c��5�ł��邱�Ƃ���A���K�R�c�S�̂Ƃ��ẮA��ԑ��9���Ґ�����Ă���B�v�Z���Ă݂�A���K�R�c�̐�ԕۗL���ʂ́A�v271��ɒB����B����́A�@�B���R�c�ۗ̕L����155��̖�2�{�ɓ���������̂ł���B
�@���̐}�\�ʂ�Ƃ���A�C����͂́A�����C�����c1�݂̂ł���B���K�R�c�ɂ��Ґ�����Ă�����˖C���c���@�B���R�c�ɂ́A�Ґ�����Ă��Ȃ����Ƃ������ł���B
�@�R�c�����͂́A�_�����c�͕Ґ�����Ă��炸�A�y�������c�ƒ�@����̂ݕҐ�����Ă���B
�@�h��C���̏ꍇ�ɂ��A�h��C�A���ł͂Ȃ��h��C����Ƃ��ĕҐ�����Ă���A�H�������H���A���ł͂Ȃ��H��������Ƃ��ĕҐ�����Ă���B���̑��ΐ�ԁA�㖱�A�d�q��A�ʐM�A���w���̕Ґ��K�͂́A���K�R�c�Ɠ���ł���B
�@�S�ʓI�Ɍ���ƁA���̐}�\�ʂ�Ƃ���A�k���N�@�B���R�c�̐�͂́A���������I�ł���B����A���̂悤�ȕҐ������m�Ȃ��̂Ƃ���A���̂悤�ɕҐ��������R�����Ȃ̂��l���Ă݂邾���̖��ł���悤�ł���B��ԕۗL�䐔���������Ȃ��_�ɂ����āA2����펮�\�A��ԌR�c�Ɨގ����邪�A�S�ʓI�ȕҐ��\���́A�����Ƒn���������ƌ�����B
�B�@�b�R�c �| ���620����܂ފe�푕�b�ԗ�1,000�]��ȏ�ۗL�����d��������
 �@�k���N�̋@�b�R�c�́A��ԗ��c5���厲�ɍ\������Ă���B
�@�k���N�̋@�b�R�c�́A��ԗ��c5���厲�ɍ\������Ă���B
�@���قɂ��ʓr�̋@�B���������c��C�����c�́A�Ґ�����Ă��Ȃ��B
�@��ԗ��c�́A��ԑ��4�ƌy��ԑ��1�A�@�B���������1�A�����C�����2�ō\������邱�Ƃ���A�R�c�S�̂Ƃ��ẮA��ԑ��20�A�y��ԑ��5�A�@�B���������5�A�����C�����10�ō\�������B
�@���ǁA�R�c�S�̂̐�ԕۗL���ʂ́A620��A�y��ԕۗL���ʂ�200��A���b�ԗ�215��A�����C180��Ƃ��� 가공할
���l�ɒB����B�@�B���R�c�̐�Ԑ�͂𑊓��y�ʉ�����������ɁA�@�b�R�c�ɑS�Ă̗͗ʂ��W�������v�Z�ł���B�k���N�̐��K�R�c�́A�����ύt�̎�ꂽ��͍\����
���̂Ɣ�ׂāA�@�b�R�c�Ƌ@�B���R�c�́A�ʂ����ČR�c�P�ƍ�킪�\�Ȃ̂��Ǝv�����炢�ɋɓx�ɕs�ύt�Ȑ�͍\���������Ă���B�k���N�̋@�b�R�c�́A����1�ɉ߂��Ȃ����Ƃ���A���̕Ґ��\�́A
���̂܂�820��ԌR�c�̕Ґ��ł���B
�C�C���R�c
 �@�C���R�c�́A�k���N�̊O�ɂ́A���\�A�R�Ґ�
�ł����T���o���Ȃ����قȕҐ��ł���B�k���N�̖C���R�c�́A���˖C6���c�Ǝ����C6���c�ō\������Ă���B�@�b�R�c��@�B���R�c�Ɠ��l�ɁA�C���R�c���x���z���ē��������Ґ��`�Ԃ��ƌ�����B
�@�C���R�c�́A�k���N�̊O�ɂ́A���\�A�R�Ґ�
�ł����T���o���Ȃ����قȕҐ��ł���B�k���N�̖C���R�c�́A���˖C6���c�Ǝ����C6���c�ō\������Ă���B�@�b�R�c��@�B���R�c�Ɠ��l�ɁA�C���R�c���x���z���ē��������Ґ��`�Ԃ��ƌ�����B
�@
�@
�@
�@
![]()
�ŏI�X�V���F2003/06/22